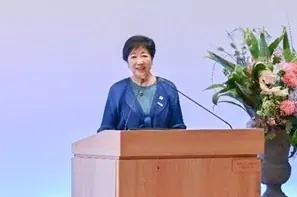都が発表「TOKYO H2」始動、FCタクシー大量導入へ
ベストカレンダー編集部
2025年9月3日 21:51
TOKYO H2始動
開催日:9月3日

官民連携で動き出した「TOKYO H2」──水素を“使う”都市へ
東京都は2025年9月3日18時48分に、官民連携プロジェクト「TOKYO H2」の始動を発表しました。発表は東京都により行われ、目的は都内における水素エネルギーの需要拡大と早期の社会実装化を図ることにあります。
特に走行距離の長い商用車両での水素活用を重視しており、運輸部門の脱炭素化と水素利用の拡大を両立させることを狙いとしています。今回の発表は、全国初の燃料電池(FC)タクシーの都内大量導入開始に合わせたもので、燃料電池商用モビリティを起点に「水素を使う」アクションを加速する点が特徴です。
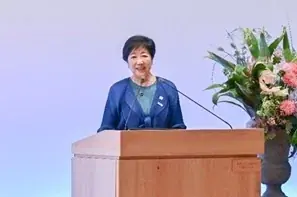
プロジェクトの位置づけと狙い
「TOKYO H2」は、燃料電池商用モビリティをはじめとした水素利用の普及を、官民が連携して加速させることを目的としています。プロジェクトは、エネルギーの安定供給や脱炭素化に資する水素を様々な分野で活用する仲間を広げることを基本方針としています。
東京都は既に燃料電池バスの導入など先行的な取り組みを進めてきており、本プロジェクトはそれらの延長線上で、国内初となる燃料電池タクシーの大量導入を契機に、タクシーに限らずバスや物流など運輸・物流分野全体で燃料電池商用モビリティの導入を促進することを目指します。

目標とロゴに込めた意味──数値目標とブランド設計
東京都は燃料電池商用モビリティの普及目標として、2035年度に約10,000台を掲げています。これは都市交通の脱炭素化を進めるうえでの明確な数値目標であり、計画的な普及とインフラ整備が求められます。
プロジェクトロゴは「H」に複数の意味を持たせており、Hydrogen / Human / Hope / Harmony / Heroの各語を想起させる設計です。さらに「2=to」によって様々なモノとつながり未来へ進むイメージを表現しています。ロゴやデザインの統一は、街中での“見える化”を意図しており、一般市民の理解と関心を高めるためのコミュニケーション戦略となります。

取り組みの具体例
プロジェクトでは以下のような具体的な施策を想定しています。導入の軸は商用モビリティですが、応用は幅広く想定されています。
- 燃料電池タクシー、バス、物流車両など商用モビリティの大量導入促進
- 水素供給インフラの整備促進と安定供給の確保
- 産業を超えた連携を通じた水素バリューチェーンの構築(つくる→つかうの一体化)
- 市民向けの見える化施策や体験イベントによる理解促進
これらを通じて、行政と企業・団体が連携して水素を社会実装するための実証・展開を加速させる方針です。

発表会と現地イベントの詳細──多面的な“水素体験”
プロジェクトの始動に伴い、令和7年(2025年)9月3日(水)に発表会等が開催されました。会場ではプロジェクト発表のほか、燃料電池商用モビリティの展示や水素体験イベントが行われ、様々な角度から水素エネルギーの活用を伝える構成となっていました。
発表会では行政、製造、運輸の代表者が登壇し、プロジェクトの意義や今後の連携について発表と挨拶が行われました。会場の展示や体験コーナーでは、技術と生活の接点を実感できる多様な取り組みが紹介されました。
発表会と関連イベントの構成
発表会・イベントは大きく三つのプログラムで構成されていました。各プログラムは公共輸送・展示・体験という相補的な構成で、水素の「見える化」と「使う体験」の両方を提供しています。
- プロジェクト発表会
登壇者の主な挨拶は以下の通りです。発表の趣旨説明と今後の協力関係についての言及がありました。
- 小池百合子(東京都知事)挨拶(プロジェクト発表)
- 佐藤恒治(一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会会長、トヨタ自動車株式会社代表取締役社長)挨拶
- 川鍋一朗(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会会長、日本交通株式会社取締役)挨拶
- FCタクシー出発式
燃料電池商用モビリティ(複数車種)展示、フォトセッション、出発見送りが実施されました。これは全国初の燃料電池タクシーの都内大量導入開始を象徴するイベントです。
- 水素体験イベント
具体的な展示と体験は次の通りです。市民が実際に水素に触れ、味や使用感で理解できる内容が並びました。
- クラウン(燃料電池車)のカットモデル展示
- 燃料電池フォークリフトや水素自転車の展示
- 水素グリラー・水素石釜・燃料電池キッチンカーによる調理の試食
- 水素焙煎コーヒーの試飲
関係者の発言から見える方向性
発表会での主要登壇者は、それぞれの立場から水素の重要性と連携の必要性を述べました。以下に発言の要旨を整理します。
これらの発言はプロジェクトの方向性を示すものであり、行政・産業界・事業者の協働が水素社会実現に向けた鍵であることが共通認識として示されました。
- 小池百合子(東京都知事)
- 気候危機やエネルギー安定確保の課題を挙げた上で、脱炭素の鍵が水素にあると述べました。今回の取り組みが日本で初めて燃料電池タクシーを大量導入する試みであり、都民が水素社会を身近に感じられる機会を通じて「世界に誇る、水素社会・東京」の実現を目指す旨を示しました。
- 佐藤恒治(一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会会長/トヨタ自動車株式会社代表取締役社長)
- 日本における水素社会実現には「社会実装」を増やすフェーズに移行したと説明しました。水素普及の鍵は産業間連携であり、つくる側から使う側まで一体となったバリューチェーンの構築を強調しました。タクシー、バス、物流事業者、インフラ事業者と連携し、商用モビリティを軸にした水素利用モデルを作る方針を示しました。
- 川鍋一朗(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会会長/日本交通株式会社取締役)
- タクシー業界にとって水素タクシー導入は新たな進化の第一歩であり、環境対策と公共交通の使命を果たしつつカーボンニュートラルを次世代へ継承する責務があると述べました。プロジェクトの下で行政や関係者と協力し、持続可能な都市交通のモデルを国内外へ広げる意向が示されました。
これらの発言から、プロジェクトは単なる展示イベントにとどまらず、実証→展開→普及のサイクルを回す意図で設計されていることが読み取れます。
関連URLと資料参照
東京都の公式情報は次の関連リンクで確認できます:https://www.metro.tokyo.lg.jp/
公式発表にはプロジェクト概要、発表会の模様、登壇者リストなどが含まれます。関係者や事業者はこれらの資料を参照し、参加・連携の検討が進められる見通しです。
まとめ(重要事項の整理)
以下の表に本記事で取り上げた「TOKYO H2」プロジェクトの主要情報を整理します。数値目標、開始日・発表日、主要イベント、登壇者、展示・体験の内容などを網羅しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト名称 | “TOKYO H2″(トウキョウ エイチトゥ) |
| 発表元・発表日時 | 東京都(2025年9月3日 18時48分) |
| 目的 | 燃料電池商用モビリティをはじめとした「水素を使う」アクションを官民連携で加速し、需要拡大・早期社会実装化を図る |
| 普及目標 | 2035年度に約10,000台の燃料電池商用モビリティ導入を目指す |
| プロジェクトロゴの意味 | Hに複数の意味(Hydrogen / Human / Hope / Harmony / Hero)、“2=to”でつながりを表現 |
| 発表会開催日 | 令和7年(2025年)9月3日(水) |
| 発表会の主な構成 | ①プロジェクト発表会(主要挨拶) ②FCタクシー出発式(展示・出発見送り) ③水素体験イベント(展示・試食・試飲) |
| 主な登壇者 | 小池百合子(東京都知事)/佐藤恒治(一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会会長、トヨタ自動車代表取締役社長)/川鍋一朗(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会会長、日本交通取締役) |
| 体験・展示内容(主要) | クラウン(燃料電池車)カットモデル、燃料電池フォークリフト、水素自転車、水素グリラー・水素石釜・燃料電池キッチンカーによる調理の試食、水素焙煎コーヒーの試飲、燃料電池商用モビリティ展示 |
| 関連リンク | https://www.metro.tokyo.lg.jp/ |
上記は東京都の発表に基づく情報であり、プロジェクトは官民が連携して水素の社会実装を進める取り組みとして位置づけられています。示された数値目標やイベント構成、登壇者の発言からは、交通分野を中心に水素利用を広げる具体的な方針が示されています。
参考リンク: