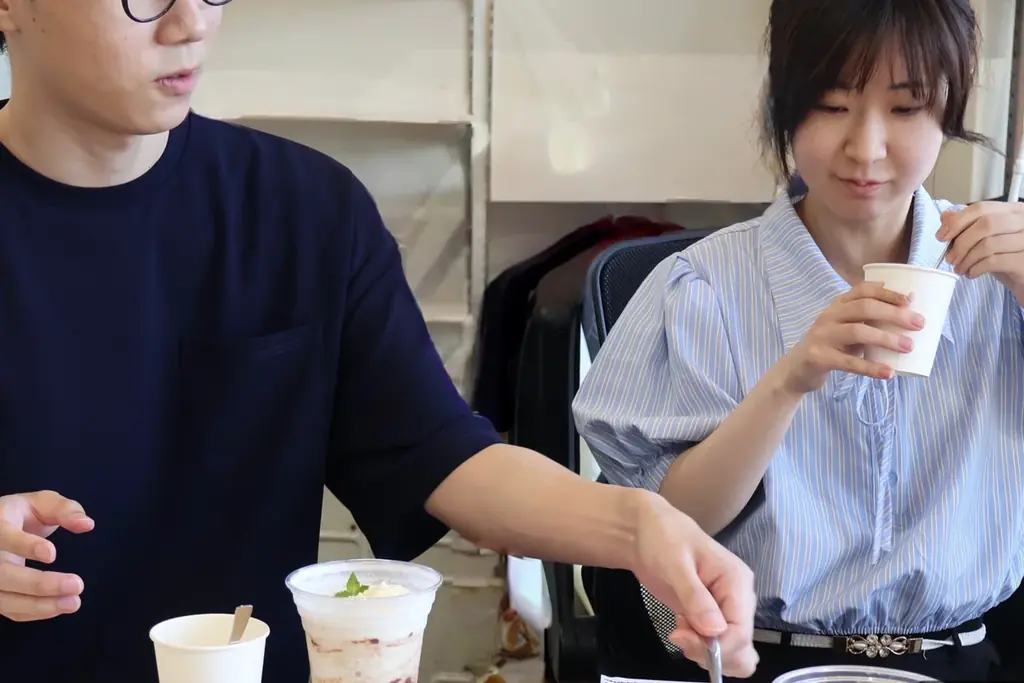8/23・8/30開催 学生と福祉でつくる期間限定カフェ「つむぐ」
ベストカレンダー編集部
2025年8月19日 10:22
つむぐプレオープン
開催期間:8月23日〜8月30日

学生と福祉事業所が共につくる地域の居場所 ― 期間限定カフェ「つむぐ」プレオープン
株式会社 道(本社:大阪市東淀川区、代表取締役:木村一雄)が運営する就労継続支援B型事業所「ミシン工房 道の空」は、大阪経済大学浅田ゼミ(注:本年5月から関西大学)と協働し、地域密着型カフェ「つむぐ」を期間限定でオープンします。プレオープン日は2025年8月23日(土)と8月30日(土)で、プレスリリースは2025年8月19日 09時06分に公開されました。
このカフェの特徴は、福祉事業所の利用者が単に「支援される側」ではなく、学生と「仲間」として店舗運営に主体的に関わる点にあります。店づくりやメニュー開発、接客までを通じて利用者にとってやりがいや誇りを生み、学生にとっては実店舗による実践的な学びの場となります。

開催概要と会場の基本情報
プレオープンは2日間、レンタルキッチンスペース『BlanCo.』にて行われます。住所やアクセス、営業時間、問い合わせ先などの実務的な情報が定められており、来訪予定者や関係者へ明確に伝えられています。
以下に会場の要点を示します。営業は当日の10:30〜17:00です。連絡先や具体的な所在地も明記されています。
- 開催日:2025年8月23日(土)、8月30日(土)
- 会場:BlanCo.(レンタルキッチンスペース)
- 住所:大阪府大阪市城東区今福西1-1-33(地下鉄鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩5分)
- 営業時間:10:30〜17:00
- 電話:080-7220-4268(担当:木村)

提供メニューと現場での役割分担
カフェ「つむぐ」は「誰でも気軽に立ち寄れてゆったり過ごせる」ことをコンセプトにしています。店内は憩いの場であると同時に、障がいのある方のアートや手仕事に触れることで地域のコミュニティが形成されることを目指しています。
メニューはコッペパンやフラッペ、アイスコーヒーなどを中心に設定されています。提供価格帯はコッペパンが500円〜600円、フラッペが550円〜600円、アイスコーヒーが450円となっています。

具体的なメニュー一覧(表記はプレスリリースに準拠)
下記はプレオープンで提供されるメニュー項目です。学生の考案メニューや事業所で育てたハーブを活用した品目も含まれます。
- ① クリーミー生ハムコッペ
- ② たまごと炙りチーズのごちそうコッペ
- ③ 自然の恵みたっぷり海老アボガドコッペ(バジル使用)
- ④ オリーブしらネギコッペ(学生考案メニュー)
- ⑤ 桃と紅茶のくつろぎフラッペ(ミント使用)
- ⑥ バナチョコフラッペ(ミント使用)
- ⑦ きらめくキウイのごほうびフラッペ(ミント使用)
- ⑧ サイドメニュー:ぽてまるバター塩/じゃがいもの冷製スープ
- ⑨ 焦がしバナナキャラメリゼ(ミント使用)
- ⑩ バラエティフルーツコッペ(ミント使用)
- ①① アイスコーヒー
- ①② アイスカフェラテ
特に学生考案の「オリーブしらネギコッペ」は、子どもにも野菜や魚を美味しく食べてもらいたいという発想から生まれました。クセの少ないしらすを用い、玉ねぎの自然な甘さとしらネギのシャキッとした食感、さらにチーズをのせトースターで香ばしく焼き上げることで、子どもや大人の双方に受け入れやすい優しい味に仕上げられています。
また、③や⑤〜⑦、⑨〜⑩で使用するバジルやミントは、就労継続支援B型事業所の利用者が事業所内で育てたものです。植物を育てることは作業の一環であると同時に、日々の生活リズムづくりや達成感の源となり、育てたハーブが店のメニューに使われることで利用者の誇りややりがいが具体化します。

プロジェクトの経緯と教育・福祉・地域連携の仕組み
この取り組みは2021年に始まった「くすのきエール・マルシェ」から発展しています。くすのきエール・マルシェは、障がいのある方が製作する手作り商品(旧称:授産商品)を学生が販売する活動としてスタートし、これまでに16回開催されてきました。
当初は学園祭の模擬店が中止になったことを契機に学生たちが地域との接点を求めたことが出発点です。学生が事業所から商品を仕入れ、事業所の特色や商品の魅力を自ら伝えながら販売することで、学生は仕入れから販売に至る経営の一連の流れを学び、事業所側は商品の改良や販路拡大のためのPDCAサイクルを回してきました。

運営体制と外部専門家の参画
今回のカフェ運営には、大阪経済大学浅田ゼミの学生主体の取り組みに加え、同大学の福学地域連携プロジェクトとして中小企業診断士登録養成課程修了者2名が参画し、事業計画立案や進行管理、専門的助言を行います。これにより、教育的価値と実行力の両面が高められています。
プロジェクトは「学生の学び」「福祉の活性化」「地域経済の循環」を同時に実現することを狙いとし、教育と福祉、地域連携を融合した実践モデルとして位置づけられています。大学と福祉事業所が一体となり、実際の現場でビジネスを経験することで、学生はマーケティングや会計などの実務スキルを現場で習得します。

利用者の主体性と成果の見える化、今後の予定と連携
カフェでの利用者の役割は、ハーブ栽培やメニュー試作への参加、制服の縫製など多岐にわたります。これらは単なる作業ではなく、自分の仕事が顧客の満足や店舗運営に直結しているという実感を育みます。
ハーブが店内に飾られ香りが広がる瞬間や、自分が関わったメニューが注文される場面を通じて、利用者にとっての達成感や誇りが日々蓄積されることが想定されています。そうした経験は将来的な就労機会の拡大や障がい者雇用の促進にもつながることが期待されています。

今後のスケジュールと計画
期間限定カフェはゴールではなく第一歩と位置づけられ、以下のような予定が示されています。
- 2025年11月下旬:大阪経済大学主催の親子向けイベント「キッズスマイルフェスタ」へ参加予定
- 他大学との連携:大学間を超えた学生同士の協働を予定
- 2026年春:クラウドファンディングを実施予定(カフェの継続展開のための資金調達とプロジェクトの発信)
- 中長期:常設型カフェの実現や障がいのある方の新たな就労機会の創出を視野に入れる
これらの予定は、地域のなかで学生と福祉がリアルに関わる機会を増やし、学びや交流の幅を広げることを意図しています。得られた経験を検証し改善を繰り返すことで、持続可能なプロジェクト運営を目指します。

運営主体と問い合わせ先、事業所の紹介
プロジェクトの中心となる組織情報や連絡先は明確に公開されています。運営主体としての株式会社 道とその事業所、浅田ゼミの役割が整理されています。
以下に運営主体と関係団体の概要、問い合わせ先を示します。関係者や取材希望者はこれらの情報を基に連絡をとることが可能です。
- 運営会社
- 株式会社 道(設立:平成23年4月)代表取締役:木村一雄。就労支援事業に特化し、訪問介護事業所や就労継続支援B型事業などを展開。
- 事業所
- 就労継続支援B型「ミシン工房 道の空」:大阪市東淀川区に所在。縫製・刺繍等の生産活動を通じた支援を行う。
- 大学側
- 大阪経済大学 浅田ゼミ(情報社会学部):地域課題に向かいビジネスを実践することを重視し、くすのきエール・マルシェ等の実践型学習を実施。福学地域連携プロジェクトとして中小企業診断士登録養成課程修了者2名が参画。
- 会社所在地・連絡
- 株式会社 道 住所:大阪府大阪市東淀川区菅原4-11-1 電話:06-6990-1261 FAX:06-6990-1262 法人HP:株式会社道
- プレオープン会場の連絡先
- BlanCo.(レンタルキッチンスペース)住所:大阪府大阪市城東区今福西1-1-33 電話:080-7220-4268(担当:木村) 営業時間:10:30〜17:00
- お問い合わせ(事業全般)
- 会社:06-6990-1261 サービス管理責任者:木村 優介 080-7220-4268
上記の情報はプレスリリースに基づくもので、運営体制や問い合わせ先が明記されています。事業の性格上、教育・福祉・地域の連携が不可欠であり、それぞれの役割分担と専門性が組み合わさってプロジェクトが進められている点がわかります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主催・運営 | 株式会社 道(就労継続支援B型「ミシン工房 道の空」)×大阪経済大学 浅田ゼミ(本年5月から関西大学) |
| プレオープン日 | 2025年8月23日(土)、8月30日(土) |
| 会場 | BlanCo.(大阪市城東区今福西1-1-33)地下鉄鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:30〜17:00 |
| 提供メニュー(価格帯) | コッペパン 500円〜600円、フラッペ 550円〜600円、アイスコーヒー 450円。学生考案メニューや事業所で育てたハーブを活用。 |
| プロジェクトの特徴 | 学生が実店舗運営を通じて実践的学びを得ること、利用者が主体的に関わりやりがいや誇りを持てる場づくり、地域経済との循環を目指す |
| 過去の実績 | 2021年開始の「くすのきエール・マルシェ」をこれまで16回開催 |
| 今後の予定 | 2025年11月下旬:キッズスマイルフェスタ参加予定、他大学連携、2026年春:クラウドファンディング実施予定 |
| 問い合わせ | 株式会社 道 電話:06-6990-1261 / サービス管理責任者 木村 優介 080-7220-4268 / BlanCo. 080-7220-4268(担当:木村) |
本記事ではプレスリリースに記載された情報を整理し、開催日時、会場、提供メニュー、運営主体、プロジェクトの背景と今後の計画までを網羅して伝えました。教育的観点と福祉的観点が同時に重ねられた本プロジェクトは、地域連携によるビジネス実践の一例として注目されます。