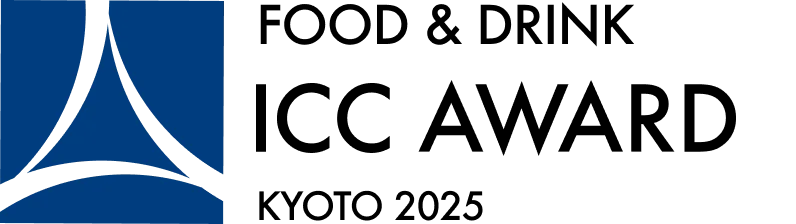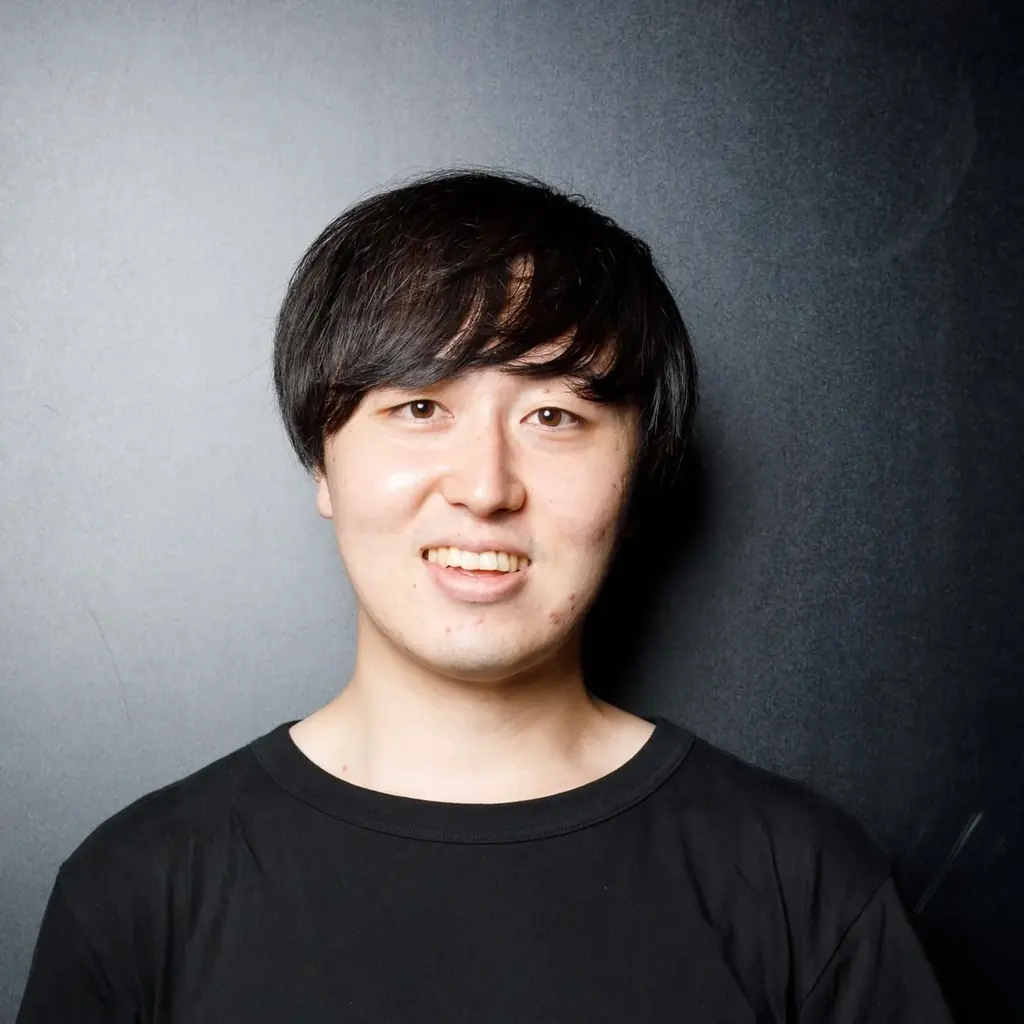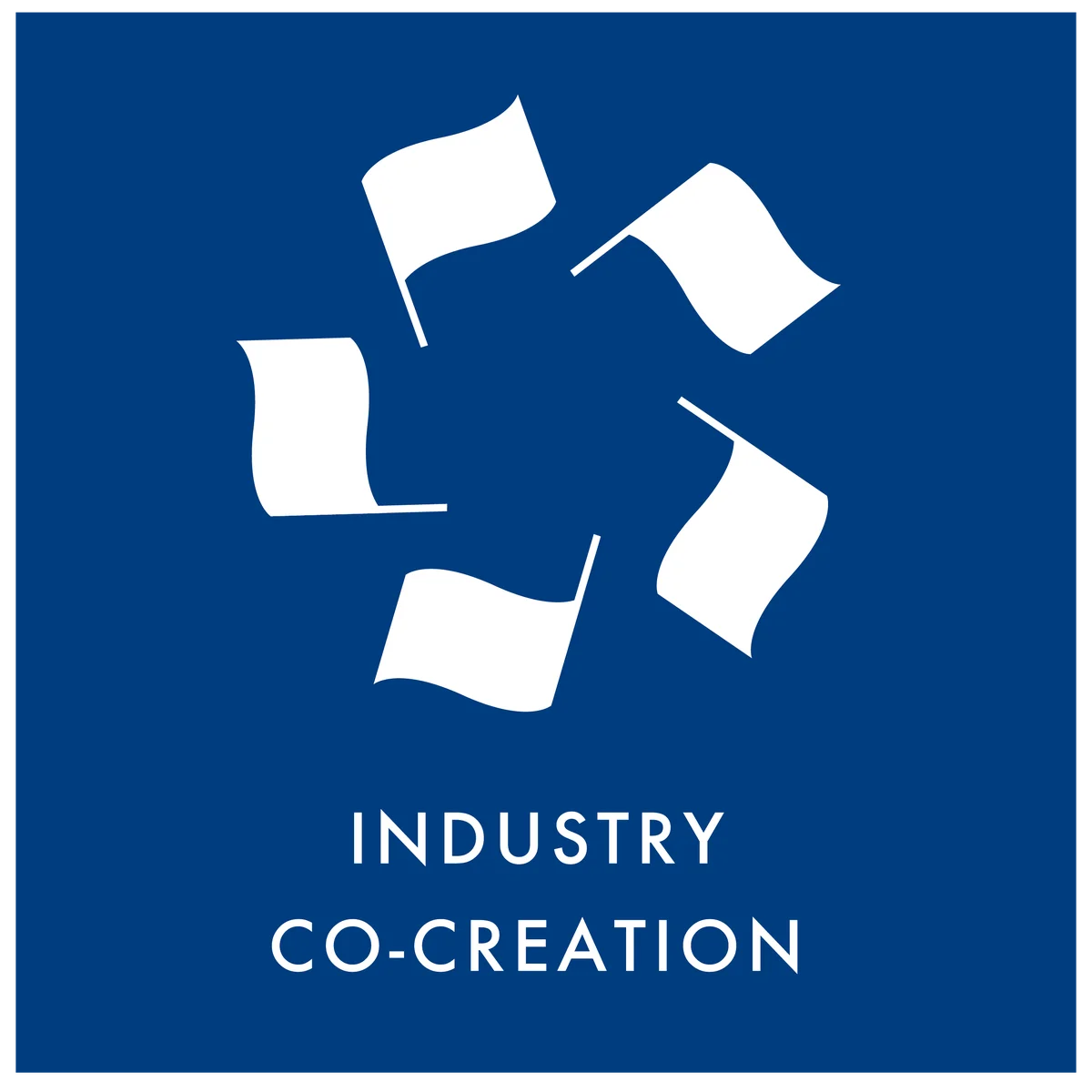9月1日開始 yuppa、ICC KYOTOでまぜそば試食
ベストカレンダー編集部
2025年8月13日 18:53
yuppaのICC出展
開催期間:9月1日〜9月4日
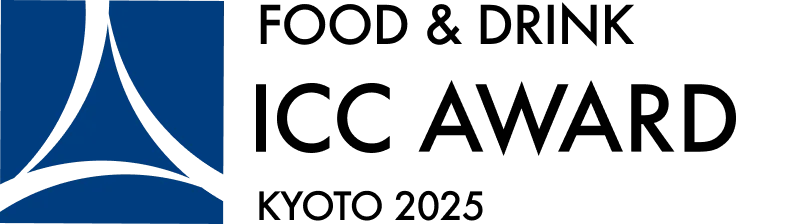
yuppa、京都での大舞台に出展 — ICCサミット KYOTO 2025 フード & ドリンク アワード参加の概要
京生湯葉を用いたヘルシーファストフードブランドyuppa(運営:株式会社yuppa、本社:東京都大田区、代表取締役:渡邊尋思)は、2025年9月1日から9月4日に京都で開催される「Industry Co-Creation (ICC) サミット KYOTO 2025」のフード & ドリンク アワードに出展することを発表しました。プレスリリースは2025年8月13日15時45分に公表されています。
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」をコンセプトとする日本最大級のビジネスカンファレンスで、毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加する場です。今回のフード & ドリンク アワードは全国から集まった18社が参加し、審査員とオーディエンスによる試食評価でアワードが決定します。

出展の位置づけと提供内容
yuppaは当イベントで、ブランドを象徴するプロダクトのうち「ORIGINAL MAZESOBA yuppa」のみを提供します。提供は試供品サイズで行われ、来場者・審査員による試食評価の対象となります。
当日の提供については「当日はORIGINAL MAZESOBAのみ提供いたします」、および「当日は試供品サイズで提供いたします」という注意書きが明記されています。来場者は一口サイズの製品でyuppaの味や栄養設計を体験できます。

ブランドコンセプトと出展プロダクトの詳細
yuppaはブランド理念を「健康にあそびゴコロを」とし、日々の健康を手軽かつ楽しくするヘルシーファストフードを提案するライフスタイルブランドです。主素材には高タンパクな京生湯葉を採用し、具材をぐるっと湯葉で巻くスタイルを軸に、最後まで飽きずに食べられる満足感を追求しています。
商品設計は栄養面を重視しており、現代の健康志向や体型維持を意識する利用者に向けたメニュー構成が特徴です。ICCで試食提供されるプロダクトは、味と栄養のバランスを両立させた試みとして位置づけられます。
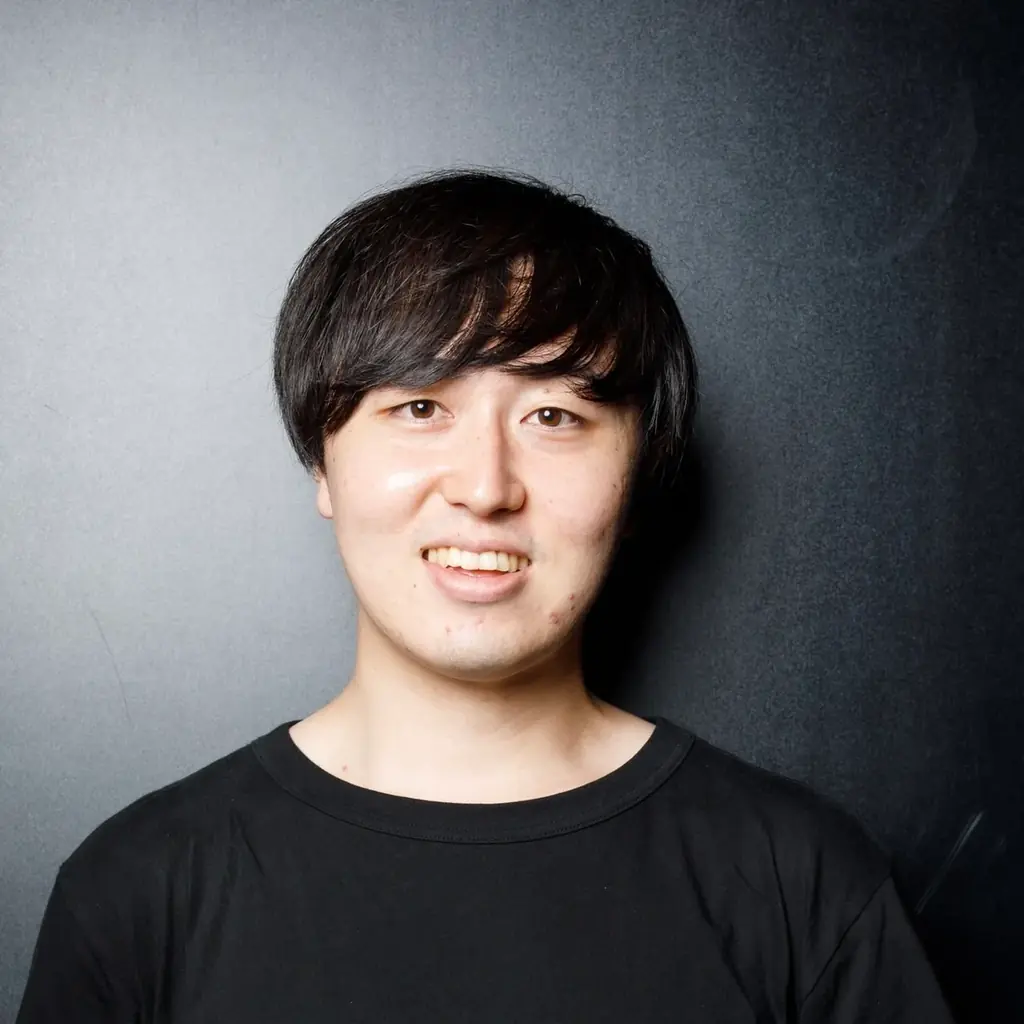
ORIGINAL MAZESOBA yuppa の特徴
ORIGINAL MAZESOBA yuppaは、従来の「生湯葉とわさび醤油」という王道の喫食方法を、独自の解釈で「生湯葉と茶そばのまぜそば」として再構築したフレーバーです。湯葉の繊細な風味と茶そばの風合いを組み合わせることで、新しい食体験を生み出すことを目指しています。
設計上は高タンパク/低脂質を志向しており、体型維持や栄養管理を重視する人々に適したプロダクトです。ICC会場では試供品サイズでの配布により、味と栄養設計を短時間で評価してもらう構成となっています。
- 主原料:京生湯葉(高タンパク)
- フレーバー:生湯葉と茶そばのまぜそば(再構築された王道の組合せ)
- 栄養設計:高タンパク・低脂質
- 提供形態:試供品サイズ(当日はこれのみ提供)

出展の背景と渡邊尋思代表のコメント
渡邊尋思代表は、ICC参加について「起業前から憧れていた舞台であるICCに参加することができ、非常に光栄」と述べています。加えて、代表の故郷である京都の地でICCに参加できることに意義を見出している旨が述べられています。
出展が持つ意味合いとして、渡邊氏は湯葉という食文化の歴史的背景と現状の課題を挙げています。湯葉は約1200年前に京都・比叡山に伝わったとされる食文化であり、和食文化の発展に寄与してきましたが、現在は需要減少・後継者不足・工業化の遅れなどにより産業規模が縮小しているとしています。

産業課題の整理とyuppaの目標
渡邊代表は、湯葉という食材の価値を従来とは異なる視点で再評価し、世界的な栄養問題(栄養不足や肥満)の解決に寄与するグローバルなヘルシーファストフードブランドの創出を目指すと表明しています。これにより湯葉産業に新たな需要を喚起し、産業のリーダーに成長することを目標としています。
ICCというプラットフォームを通じて、伝統食材を現代の食市場に適応させる試みを実証することが狙いの一つです。FUKUOKAではなくKYOTOの舞台であることにも文化的・歴史的意義を込めて出展を決めたと説明しています。
ICCサミット KYOTO 2025 の開催情報と参加形式
Industry Co-Creation (ICC) サミット KYOTO 2025(略称:ICC KYOTO 2025)は、主催がICCパートナーズ株式会社、製作総指揮が小林雅氏(同社代表取締役)とされるイベントです。開催日程は2025年9月1日〜9月4日で、メイン会場はウェスティン都ホテル京都などが予定されています。
イベントには毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加すること、参加者が朝から晩まで学び合い交流する場であることが公式に示されています。次回開催としてICC FUKUOKA 2026は2026年3月2日〜3月5日に予定されています。
フード & ドリンク アワードの仕組み
フード & ドリンク アワードは全国から集まった18社が参加するプログラムで、審査員とオーディエンスの試食評価によってアワードが決定します。参加ブランドは自社プロダクトを持ち寄り、来場者と審査員が実食して評価を行います。
yuppaはこの場で試供品を提供し、味覚評価と栄養面の訴求を通じてブランド認知と市場適合性の検証を行います。イベント情報の詳細は公式ページ(https://industry-co-creation.com/events/icc-kyoto-2025)に掲載されています。
会社情報、問い合わせとまとめ
以下に株式会社yuppaおよびICCサミット KYOTO 2025に関する主要情報を整理します。会社概要としては、株式会社yuppaが「yuppa」ブランドを運営し、実店舗は東京都港区に2025年秋オープン予定、代表取締役は渡邊尋思、所在地は東京都大田区となっています。
問い合わせ先としては、担当者名とメールアドレスが明記されています。出展や製品についての詳しい質問は代表の渡邊尋思 宛てにメールで連絡できます。
- 会社名
- 株式会社yuppa
- ブランド
- Healthy Fast Food「yuppa」
- 代表
- 渡邊尋思(代表取締役)
- 本社所在地
- 東京都大田区
- 実店舗
- 東京都港区(2025年秋オープン予定)
- 問い合わせ(担当)
- 渡邊尋思(メール:jinshi.watanabe@yuppa.co.jp)
以下の表はこの記事で取り上げた主要項目を整理したものです。続く段落では表の内容を簡潔にまとめて記事を締めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| リリース日時 | 2025年8月13日 15時45分 |
| 出展者 | 株式会社yuppa(代表:渡邊尋思) |
| ブランド | Healthy Fast Food「yuppa」 |
| 主素材 | 京生湯葉(高タンパク) |
| 提供プロダクト | ORIGINAL MAZESOBA yuppa(当日はこの試供品のみ提供) |
| 栄養特性 | 高タンパク/低脂質(体型維持を意識する層に推奨) |
| イベント名 | Industry Co-Creation (ICC) サミット KYOTO 2025(フード & ドリンク アワード) |
| 開催日時 | 2025年9月1日〜9月4日 |
| 会場 | ウェスティン都ホテル京都(メイン会場)など |
| 参加社数(アワード) | 18社(全国から参加) |
| ICCの参加規模 | 登壇者500名以上、総参加者1,200名以上 |
| 主催 | ICCパートナーズ株式会社(製作総指揮:小林 雅) |
| 問い合わせ | 渡邊尋思(jinshi.watanabe@yuppa.co.jp) |
| 公式イベント情報 | https://industry-co-creation.com/events/icc-kyoto-2025 |
本記事は株式会社yuppaが公表したプレスリリースの内容を基に、出展の目的・プロダクトの特性・ICCサミットの概要・問い合わせ先までの主要情報を整理しました。ICCのフード & ドリンク アワードにおける試食提供は、yuppaの製品設計と栄養訴求を直接評価にかける機会であり、京都の伝統食材である湯葉を現代の消費ニーズへ接続する意図が明確に示されています。