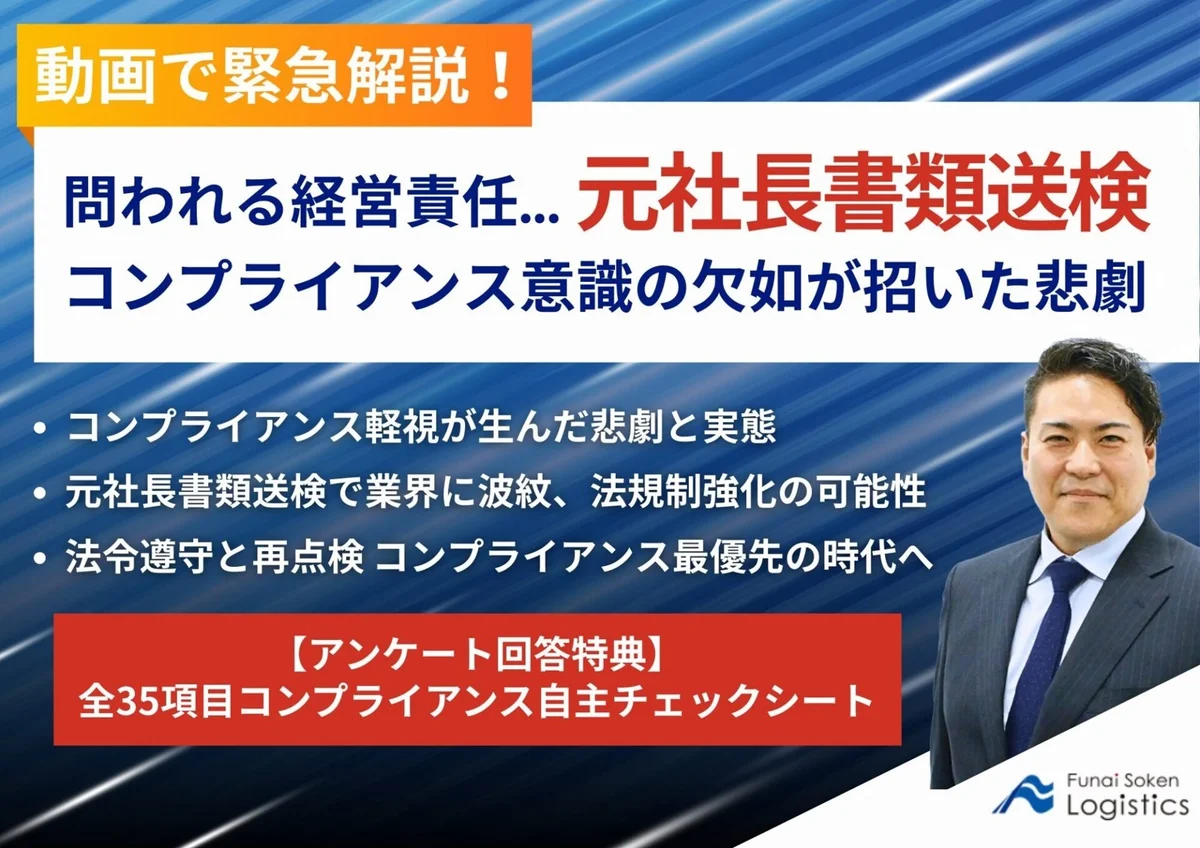船井総研ロジが運送業界の法規制強化を解説する動画を5月16日まで公開中
ベストカレンダー編集部
2025年5月12日 10:28
コンプライアンス動画公開
開催期間:5月2日〜5月16日
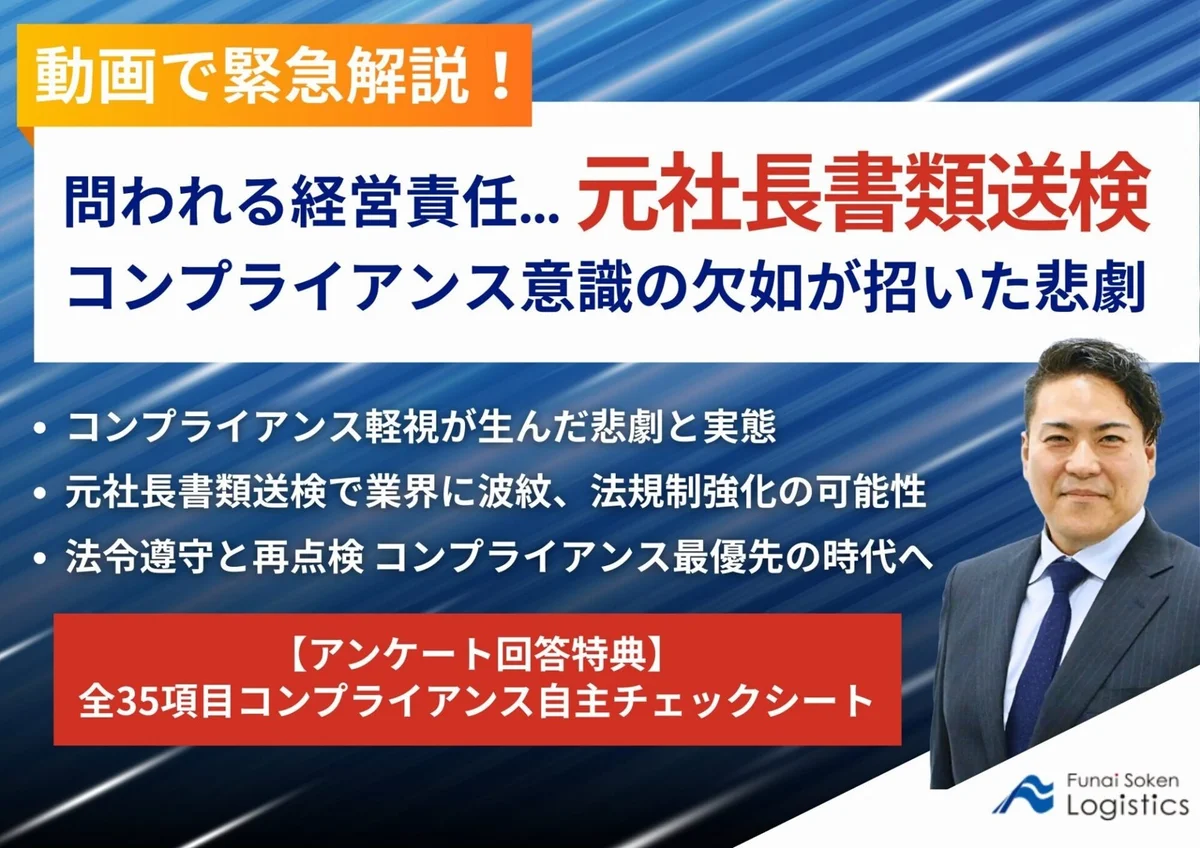
動画で緊急解説!コンプライアンス意識の重要性
2025年5月12日、船井総研ロジ株式会社は、運送業界における法規制強化や許可更新制導入の動きについて詳しく解説した無料動画を公開しました。この動画は、コンプライアンス軽視が引き起こした悲劇を背景に、今後の運送業界における重要なテーマを扱っています。
視聴申込みは簡単で、わずか30秒で完了します。動画は2025年5月2日から5月16日まで視聴可能で、視聴には事前の申し込みが必要です。申し込みは2025年5月15日まで受け付けています。

動画の内容と背景
この動画では、以下の重要なトピックについて解説されています。
- コンプライアンス軽視が生んだ悲劇と実態
- 元社長書類送検による業界への影響
- 法令遵守の必要性と再点検
特に、首都高速で発生した多重事故の原因として、運転手の体調不良を無視した強行乗務や虚偽の点呼記録、長時間労働の常態化が挙げられています。この事件は、コンプライアンス意識の欠如が引き起こしたものであり、業界全体がその影響を受ける可能性があります。
コンプライアンスの重要性と今後の対策
船井総研ロジは、運輸支局や労働基準監督署の監査対応、法務や労務管理の指導に精通したコンサルタントが、事故の深層と元社長書類送検の経緯を解説しています。コンプライアンスを経営の最重要課題と捉え、持続可能な事業運営を目指すことが求められています。
また、動画視聴後にはアンケートに回答することで、全35項目からなるコンプライアンス自主チェックシートが提供されます。このチェックシートを利用することで、自社の潜在的なリスクを早期に発見し、法令遵守の徹底に向けた第一歩を踏み出すことができます。
個別相談会の実施
船井総研ロジでは、希望者に対して個別相談会も実施しています。これは10社限定で行われ、具体的な問題に対するアドバイスを受けることができる貴重な機会です。自社のコンプライアンス体制を見直すためのサポートを受けることができるため、非常に有意義なプログラムと言えるでしょう。
船井総研ロジ株式会社の概要
船井総研ロジ株式会社は、「社員が誇れる物流企業を創る」というミッションのもと、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。新規荷主獲得や運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、幅広い支援を行っています。
また、全国から350社以上の経営者が集まる「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」を運営しており、業界の最新情報や動向を共有する場ともなっています。
会社概要
| 会社名 | 船井総研ロジ株式会社 |
|---|---|
| 東京本社 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階 |
| 大阪本社 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル |
| 設立 | 2000年5月10日 |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 連絡先 | TEL:03-4223-3163 MAIL:marketing@f-logi.com |
| WEBサイト | https://www.f-logi.com |
船井総研ロジは、物流業界の最新動向を配信しており、SNSやメールマガジンを通じて情報を発信しています。興味のある方は、ぜひチェックしてみることをお勧めします。
まとめ
船井総研ロジ株式会社が公開した動画は、コンプライアンス意識の重要性を再認識させる内容となっています。元社長の書類送検という重大な事件を受け、今後の運送業界における法規制の強化や許可更新制導入の動きが注目されています。
自社のコンプライアンス体制を見直し、持続可能な事業運営を目指すためには、今回の動画を視聴し、アンケートに回答することが一つのステップとなります。また、個別相談会を通じて専門的なアドバイスを受けることも重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 動画公開日 | 2025年5月2日~5月16日 |
| 視聴申込み締切 | 2025年5月15日 |
| コンプライアンスチェックシート | 全35項目 |
| 個別相談会 | 10社限定 |
このように、コンプライアンスの重要性はますます高まっています。業界全体で意識を高め、持続可能な運営を目指すことが求められています。
参考リンク: