片頭痛と偏頭痛の違いを知って快適な生活を手に入れよう
ベストカレンダー編集部
2025年03月16日 23時00分
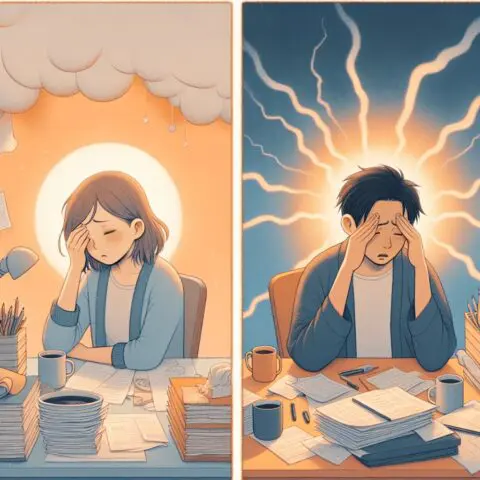
片頭痛と偏頭痛の違いを知ろう
頭痛にはさまざまな種類がありますが、その中でも「片頭痛」と「偏頭痛」という言葉がよく使われます。実際には、医学的には「片頭痛」が正しい表記であり、英語では「migraine」と呼ばれています。この言葉は古代ギリシャの医学者ガレノスが名付けた「hemicrania」に由来し、片側の頭痛を意味しています。しかし、日本では「偏頭痛」という表記も広く使われており、これはワープロの変換によるものが大きいとされています。以下では、片頭痛と偏頭痛の違いや、それぞれの特徴について詳しく説明します。
片頭痛の特徴と症状
片頭痛は一次性頭痛の一種で、頭の片側または両側にズキズキとした拍動性の痛みを伴います。以下のような症状が特徴的です:
- 頭痛が4〜72時間続くことがある。
- 吐き気や嘔吐を伴うことがある。
- 光や音に敏感になる。
- 運動をすると痛みが悪化する。
- 前兆として視覚的な症状(閃輝暗点)が見られることがある。
これらの症状により、日常生活に支障をきたすことが多く、特に生産年齢層においては経済的な損失も大きくなります。日本では、15歳以上の片頭痛の有病率は約8.4%とされ、女性に多く見られます。
偏頭痛と片頭痛の歴史的背景
「偏頭痛」という表現は、日本古来の文献にも見られ、1530年に成立した『清原国賢書写本荘子抄』には「偏はかたかたぞ。偏頭痛。正頭痛」という記述があります。このため、偏頭痛という表記も必ずしも間違いではありませんが、現在の医学では「片頭痛」が正式な用語として認識されています。学術的な論文やガイドラインでも「片頭痛」が使用されており、医療従事者もこの用語を用いることが推奨されています。
片頭痛のメカニズムと誘因
片頭痛のメカニズムは完全には解明されていませんが、神経説や血管説が広く知られています。主に三叉神経の刺激が関与しており、これにより炎症や血管の拡張が引き起こされます。片頭痛の誘因には以下のようなものがあります:
- ストレスや疲労
- 睡眠不足や過剰な睡眠
- 特定の食べ物(赤ワイン、チョコレートなど)
- 月経周期やホルモンの変動
- 天候の変化(気圧の低下など)
これらの誘因が複数重なることによって、片頭痛が発生することが多いとされています。
片頭痛の診断と治療法
片頭痛の診断は、詳細な問診や症状の確認を通じて行われます。特に、痛みの場所や性質、随伴症状の有無などが重要です。治療法としては、急性期治療と予防療法に分かれます。急性期治療には、以下のような薬が用いられます:
- トリプタン系薬剤
- 非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)
- アセトアミノフェン
予防療法には、抗CGRP抗体薬やカルシウム拮抗薬、β遮断薬などが使用されます。特に、片頭痛は治療・予防が可能な病気であるため、医療機関での診断・治療が推奨されています。
片頭痛と他の頭痛の違い
| 特徴 | 片頭痛 | 緊張型頭痛 | 群発頭痛 |
|---|---|---|---|
| 持続時間 | 4〜72時間 | 30分〜7日間 | 15〜180分 |
| 痛みの性質 | 拍動性 | 締め付けられるような痛み | えぐられるような激痛 |
| 随伴症状 | 悪心、嘔吐、光過敏 | ほとんどなし | 涙、鼻漏 |
| 有病率 | 8.4% | 20% | 1%未満 |
このように、片頭痛は他の頭痛と異なる特徴を持ち、適切な治療が必要です。特に、片頭痛の発作が頻繁に起こる場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
まとめ
片頭痛と偏頭痛は表記の違いがあるものの、医学的には「片頭痛」が正しい用語です。片頭痛は一次性頭痛の一種で、特徴的な症状やメカニズムがあり、適切な治療が可能です。生活習慣の改善や医療機関での治療を通じて、片頭痛を軽減し、より快適な生活を送ることができるでしょう。
